
何事も、ポジティブに捉えよう、というのを大切にしていた時代がありましたが、
それはベターであるがベストではない、という考えに至りました。
ポジティブシンキングは、強引に、物事を楽観的に解釈しがちで、
物事の穴を見落とす危険性を備えた方針であると結論づけました。
わかりやすく言えば、
例えば仮に、財布をなくしてそれが返ってこないとします。
通常であれば、かなり悔しく、ネガティブにとらえやすいことであります。
それを、ポジティブシンキングで対処しようとすれば、
「これで新たな財布に変える理由になった」
「拾ったその人はものすごいお金に困っていた人かもしれないので社会貢献だ」
など、対処することができます。
ネガティブに捉えれば
「ついてないやつだ」
「お金がなくなってしまった」
など、いろいろ出てきます。
ここにおいて新たなシンキング手法「水平シンキング」がベストだと考えました。
「いいことだ」とポジティブで終わると、その後再発を繰り返す可能性がある。
よって、いいことともせず、悪いことともせず、「両方の視点を眺める」のです。
「ポジティブに捉えれば、~だし、ネガティブに捉えるとすれば~だよな。」
これを、すべてに当てはめます。
そこに、感情を添付せず、そこから導き出せる、次への成長材料は何か、この事実が訴えかけてくるメッセージとは何か、
それだけに注目します。
なぜ、それが大切かというと、
一方の視点しか持っていない人になると、考えが偏り、偏見につながったり、
物事を多面的に捉えられず、一方向の思想が強い、盲目的な人間になってしまうからです。
私の癖かもしれませんが、
「本当にそうなのか?」と毎回思ってしまいます。
「こっちの視点もあるよな」と。
物事において、人において、
ポジティブ、ネガティブを眺め、メッセージを汲み取り、次に活かす、これでいいです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

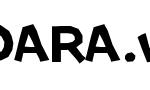










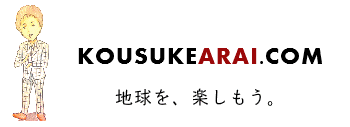
この記事へのコメントはありません。