
この一ヶ月
かつてないくらい様々な会社・業態の方との連絡を取り合い
調整していく機会をいただいています。
チームを組んでいるかのような感覚になっています。というか、そう思わないといけない場面がありました。
こちら側が発注を依頼する、何かを注文する側になり相手にとってはこちらはお客さんという立場において
一方でその業者さんたちがいなければ、自分が実現したいプロジェクトを実現することができないわけですから、
共同体のようなものです。つまり、お客さんだから、と云う感覚を持っていては事業はできないのではないかという仮説を立てました。
先方も忙しい中でスケジュールを組み、こちらのプロジェクトが成功するように仕事を進めていってくれるわけです。
私は、形式上お客さんでありますがチーム員の一つでしかなく、そのプロジェクトを実現するために調整していくだけなのです。
だから、お互いのコミュニケーションの中で感謝を表明していくことが非常に大切であるということ。
一歩進むごとに、「ありがとうございます。」で何ら問題ない。
表明しないと伝わりません。
察してもらおう、私はお金を払う立場だから当然だ、と思っていてはいい成果は出せません。
これは、プロジェクトの中だけの話ではなく、すべてのことに通ずる基本的法則でしょう。
資金配分の調整役が、依頼主である、だけです。支払い、ではなくその後の事業を成立させるための
資金移動、のような感覚なのです。
この感覚は今後、ずっと仮にどんなプロジェクトを遂行していくにあたっても、
本気で大切なことだから文に残そうと思いました。
例えば、ビルの一室を借りて店舗を作ろうとする場面であれば、
「この家主さんと一緒に店舗を作る」という気持ちを持つということです。
一緒に、事業をやるんだ、ということです。私は借主ではありません。
パートナーなのです。これに気づく一ヶ月でした。
まだ続きますが、そういう、人間的な胆力が求められるのがこの社会なのではないか。
相手のスタンスを、理解する。相手は人間であり、相手の要望もある。
その日、その時で状況も気分も変わる。今日はよくても、明日は大変だったりする。だから、常に相手の時間をいただいるということを忘れずに、
相手と共によくなっていくにはどうすればいいか、その一点からぶれずに交渉にあたる。
10社が関わっていれば、10社の立場とスケジュール感があり、コスト感や利益目標も違う。
私は共感力が欠けているため(正確にはかけているということに気づいた。ストレングスファインダーの結果参照。)
その代わりとして想像力を駆使していくということを身につけました。
感性としてないのだから、想像するしかないんですね。
例えば自分が平気だから、他の人も平気だろう、と思ってしまうのです。
しかしそうではなく、お互いが共感できないこともあるわけだから、想像をしていく。
過去の経験から、推察する。だから経験が大事なんだと思いました。
経験という統計データからだされる確率の高いものを想像するということです。
失敗していくことが大事なのは、そこに確かなデータが蓄積されるからです。想像では
限界なんですね。実感が伴わない。
MBAとかも、以前めちゃめちゃ興味ありましたが、その時に学ぶより、
その時よりも興味は失われたにもかかわらず、今の方がはるかに学ぶ吸収力が上がっていると思います。
関連本を読んでみましたが、
以前は「は?」って思っていた箇所が、「なるほど」に変わりました。よくある聞き応えのいいフレームワークとか、
ただかっこつけたいだけのクソ無駄知識だと思っていましたが、どうやらそうでもないな、と思えるようになりました。
知識が使われる場面を、実際に経験したからに他なりません。
勉強においても、まず経験→勉強の方が学ぶ効率は良さそうです。よって、経験を先に出来る場合は先にしておき、
その後勉強する、という流れがいいのではないかと考えます。
現在、株式投資と為替の勉強を中心に行っていますが、その場合もまずは株を買うことから始めました。
それで、損を出しました。これが大事なんです。損の痛みを持って、ではどうすれば損をしないのか、嫌だから考えまくるわけです。
値動きはどうだったのか?企業業績を分析しきれていたのか?地合いがどうだったか?
などいくらでも改善点は出てきます。
だから、あえて怪我する、というのは私のやり方ですが、先に準備してから何事も行いたい人にとかには特にオススメです。
合言葉は、まずは怪我する。です。
怪我、と言いますが、これはその後の大怪我を回避する怪我でもあり、傷も最小限であり復帰も早いため、大したことないです。怪我のうちに入らないかもしれません。
それよりもその小さな怪我が嫌すぎて先に、知識だけ詰め込んで時間を無駄にすることの方が問題です。頭でっかちになるだけです。
あくまで、「成長すること」が目標のはず。
その本質を忘れずに、実行→勉強、のサイクルを繰り返していくことが大切です。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

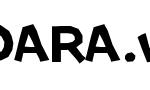










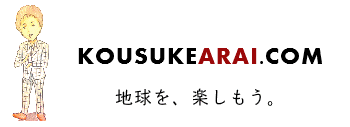
この記事へのコメントはありません。