CCC(カルチュアルコンビニエンスクラブ)創業者 増田宗昭氏から学んだ大事なこと④
- 2016/10/25
- BOOKS
- 2 comments

写真はシンガポールのマリーナベイサンズです。かなり行ってみたいですが、しばらく先でいいです。
いまは勉強、勉強、勉強。
どれほどソフィスケートされたデザインを与えられたグラスであっても、突き詰めればその機能は液体をいれておくという極めてシンプルなものであるように、
実は企画に関するこうした問いかけの答えもまた、本質的にシンプルなのだ。企画の価値とは、その企画は顧客価値を大きくするものであるかどうか、
というそのただ一点にかかっているのだから。
例えば企画会社・CCCの代表的な作品として、多くの人が思い浮かべるであろうTSUTAYA。
その特徴の一つとして挙げられるのが、深夜まで営業しているという業態だろう。
コンビニエンスストアのある風景が常態化した今日でこそ、それをもって特別なことと捉えられる向きは薄れたかもしれないが、
TSUTAYAが一般に認知される過程においては、多くの人の目にかなり斬新な試みとして写ったようだ。もっとも私は何も深夜まで営業すれば目立つだろうなどと考えて、こうした業態を取り入れたわけではない。
営業時間を長くすれば、その分儲かるだろう、と思ったわけでも、ましてや深夜まで店を開けて頑張っていることをアピールしようなどと計算したわけでも決して無い。
ただ私自身の皮膚感覚として、深夜まで映像や音楽のソフトや本などを買ったり借りたりできるほうが便利だし楽しいと感じられたから。言い換えれば、
顧客にとっての価値が大きくなると確信したからだ。そしてそうであるのなら、つまり顧客価値を高められるのであれば、いかに
オペレーションの面などでの困難がますとしても、それは克服されなければならないのだと考えた。(知的資本論/増田宗昭)
増田社長の考えが特にシンプルなのは、
常に「顧客価値」に尽きる、そこを追求してく一点ということです。
デザインという言葉を使うのは、すべては顧客価値のためであり、
最後の部分の、オペレーションを克服しろ、というのはその通りです。
とはいうものの、そうするとコストもかかるし、時間も労力もかかる、
で、
終わりにすれば、思考停止です。楽です。何もしなくていいんです。
しかし、ここからが本当の仕事であり事業であり、面白いところではないでしょうか。
これを克服できれば喜ぶ人が増えます。企画という表現をされていますが、
仕事の本質だと思います。
私は、カフェの中で500の改善を行おうと目標を掲げました。
100位は改善ができましたが、まだまだできると思っているし、全然改善しきれてないと思っています。
これを一つづつ改善して、実際にお客さんが喜んでくれるのは嬉しいです。
なぜなら、無から有を生み出したと思えるからです。何もしなければ、この喜びは生まれなかったかもしれないと
考えればそれだけでもうオールオッケーとも思えます。
どうすればもっと価値を提供できるのか。
当たり前で、ものすごい単純ですが永遠のテーマです。
考えまくること、しか今の所の解は見えませんが、それでいいと思っています。
考えて、考えて、考えつかれて、それでも考え続けて、やっと一つ見えたりします。
以前、ユニバーサルスタジオジャパンの森岡さんのことを取り上げましたが、
あの方も何かアイデアが必要な時とにかく考えをやめずにずーっと思考し続けて、
ある日急に光が差すようにパッとひらめきが降りてくることがある、と言っています。
それを聞いた時に、わかる、わかる、と思いました。あれは何なのかはわかりませんが、
閃光が走るように、一瞬で謎が解けるような感覚です。しかしそれは普段から、めちゃめちゃ考えてるから
降りてくるわけです。
思考の勝負が、現代、です。思考力の差なんです。明らかに。
肉体労働やスポーツの世界であれば、身体能力の差、が大きいですが、
このたくさんのツールに溢れた、情報化社会においては、いくらでも勉強できますし、
やろうと思えばなんでもできる時代なんですね。
よって、どのタイミングで何をやるのか、何を極めるのか、どうやって表現するのか、などいくらでも
思考していけます。
思考力がないと、もういいや、となってそこで可能性は止まってしまいます。
ありふれていますが、PFドラッガーが、知識労働社会の到来と、何十年も前から言ってますが、
それの進化系、が訪れているわけです。思考できなければ、思考できる人に従っていくしかないという現状です。
それを鍛えるには普段、どれだけ徹底的に、それも丁寧に考えられているか、です。
先ほどのオペレーションの克服、も、めんどくさいからいいや、ですぐ終わってしまうわけです。
そうではなく、丁寧に、では何から解決できるのかな、できるとすればどこからかな、と丁寧に、
そして徹底して解決できないわけがない、という確信を持って考えていくことで、初めて見えてきます。
これは私自身の課題なんですが、丁寧さ、というのがとても大切です。
わからないことがあれば、即、調べる。これも丁寧さ、です。なぜなら、調べようと思い検索すればすぐにわかる。
それを調べないのは、ただめんどくさいから、なだけです。丁寧じゃないんです。
わからない言葉が出てきたのは、ある意味チャンスなんですね。あなたは、それがわからないんですよ、とわざわざ教えに来てくれてるんです。
それに対して、スルーしまくっていく人、すぐに調べる人、で、5年、10年スパンで天と地との差になっている気がします。
顧客価値を追求する、ということは丁寧に、徹底的に思考する、ということじゃないかと、
増田社長の言葉からインスパイアされました。
そして、それは効率を追求することから始めることではない、という一文があります。
効率とは絶対的な基準なのだろうか?
確かに人間の社会は、より便利にという方向に進んできた。より便利に移動するために鉄道が敷かれ、高速道路が造られた。より便利に人と会話ができるように電話が
発明され、やがてそれはスマホに進化した。アイロンをかけなくていい形状記憶シャツ。汚れがあっという間に落ちる高圧洗浄機。
留守中に家を掃除してくれるルンバ。オートチャージしてくれるスイカ・・・。
すべてが便利な方向に進む。つまり手間を省き、効率をあげる方向へと。
しかし、効率と幸福は違う。確かに効率は便利に通じる。便利は多くの場合、快適を導くかもしれない。ただし、快適と幸福もまた、イコールではない。例えば自動車が通れない、森のなかの散歩道。移動するのに効率はよくない。しかしそこをぶらぶらと歩くとき、幸せを感じる人は決して少なくない。
そう、効率と幸福は、実は逆のベクトル上にあるものではないだろうか。そう考えて、私は「代官山T-SITE」を創った。
効率を考えるのではなく、居心地のいい空間を顧客に提供することを、第一の目標に据えて。だから実際に、テナント軍は森のなかの散歩道で結んだ。
敷地内にもともとあった襷(たすき)の樹は残した。絶対に刈るなといった。
思えば、自然ほど人間にとって効率の悪いものはない。樹であれば秋には葉を落とす。掃除だってしなければならない。夏を迎える前には、剪定する必要だってあるだろう。それだけ手間がかかる。しかし、そこを渡る風は心地よく、揺れる木漏れ日は美しい。私は代官山に、それを感じられる空間を創りたかった。
そのほうが幸せに近いのではないかと思った。代官山という土地にあって、120台分の平沖の駐車場など非効率も甚だしい。機械式のタワーパーキングにでもしたら、敷地はもっと「効率的」につかえて、売り場面積だって増やせたかもしれない。しかし、それではダメだと思った。
駐車場にクルマを停め、ドアを開けて外に出た時の開放感。それが必要だと。それは次に訪れるときのワクワク感にもつながる。
知的資本が貸借対照表に載せることができないのと同じように、こうした開放感や高揚感は数字で図ることができない。
そして数量化することができない感覚こそ、幸せの近くにあるものではないだろうか。企画会社は顧客価値の拡大を図る会社だ。
それは言い換えれば顧客の幸せや豊かさのための企画を生み出す会社ということだ。その幸せや豊かさが、効率とは異なるベクトルを持つ以上、
企画会社の組織の完成度を、効率をもって測ろうとするのはおかしい。
私がヒューマンスケールにこだわるのは、それが効率ではなく、幸福に寄り添うものだからなのだ。
もちろんヒューマンスケールの組織を構成するスタッフにわざと効率の悪い仕事をしろといっているわけではない。
効率を唯一のものさしとはするな、と言っているだけだ。
効率は目標ではない。あくまでも結果の一側面にすぎない。
最初から効率を追求してはいけないと思う。(知的資本論/増田宗昭)
わざわざ効率を下げるの意味ではないが、あくまで顧客価値をどれだけ大きくできるのか、
ここから考えないといけないわけです。
効率追求は、そこに固執すると気づかぬうちに事業崩壊を巻き起すと考えています。
なぜなら、本質であった価値を破壊するからです。価値がないものに、お金を払う人が誰がいるのか?
やった、効率化できた!でもそれ誰も買わないよね、ってもう悲しすぎます。
だから、効率追求は本質からそれないようにちゃんと監視しながらやらないと、危険なんです。
持論すぎますが、これは心から思います。なぜ、いきなり効率なのか、と。
というかその考え方自体はあまり面白くないとも思います。大企業が生産性を追求するのは、命題と思いますが
小さな企業があまりそこに固執すぎると、自爆すると思っています。価値がなんなのか、何をお客さんは買ってくれているのか、
ここを思考し続けて、本質を捉えないといけないです。勉強カフェなんかは、かなり見落としやすいと我ながら思っています。
どこが、この場所の本質的な価値なのか。
快適な勉強場所、気持ちの良いスタッフ、セミナー、居心地、とか挙げだしたらきりがないくらい総合的なんです。
でも、どれかが欠けたりしても価値が減っていくかもしれないし、そうでないかもしれない。
要は見極めです。それによってもっと大きな価値がうめるような確信がない限りは、効率化は慎重になります。一方
その中で検討した上での効率化は、どんどん行うべきです。時間ができれば、新たなサービスが作れて、
先ほどの顧客価値を増やせるからです。
今の勉強カフェはそことの戦いでもあると思っています。どこが効率化をするところで、どこをもっと追求して価値提案していくか。
判断を誤れば、たちまち無価値となる。
考え続けます。先ほど書いた通り、ある日降ってくるかもしれないです。その時に、また面白いサービスアイデアを発表できると思います。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
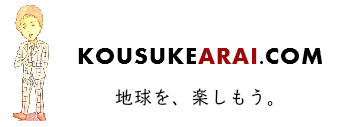

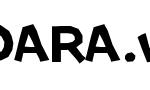









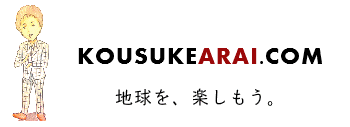
この記事へのコメントはありません。