枚方市駅前の新名所「枚方T-SITE(蔦屋書店・TSUTAYA)」を見てきた感想
- 2016/5/16
- WORK
- 7 comments

地域性に根ざした、その土地ならではの蔦屋書店や市立図書館を各地に作り上げていくことが、現在のCCCの一つの目標になっている。
本は提案のカタマリ。
そうした本を集積した書店や図書館のイノベーションが各地で進むということは、各地に知的資本を高めるための拠点ができるということを意味するはずなのだ。
CCC=カルチュア・コンビニエンス・クラブという会社の存在意義(レーゾンデトゥール)。
それを私は「カルチュアインフラ」をつくることだと創設以来、言い続けてきた。
全国に展開されるTSUTAYAは、社会にとって必要不可欠なインフラになるのだと。これからの社会生活においては道路や水道屋や送電線ばかりがインフラと呼ばれるのではなく、映画や音楽といったカルチュアもまた、人々の生活に欠かすことのできないインフラになる。
それを供給するのがTSUTAYAなのだと。(増田宗昭『知的資本論』
5月16日、大阪の枚方市駅の目の前に、大阪では初となる「T-SITE」がオープンしたということで、
増田社長の考え方に激しく共感している身として、早速見に行ってきました。
枚方駅の真ん前にあります。
注目すべきはかねがねTSUTAYA創業者の、増田宗明社長が言い続けてきた「ライフスタイル提案」の部分。
地域の人々に寝だした、「生活の拠点」「日常のワンシーンの演出」になり得るものなのかどうか。
そして、提案内容の対象は「プレミアエイジ(エネルギッシュな60歳以上の方々)」。
今回、私はユーザーとしての立場ではなく
ライフスタイル提案を追求するものの一人として、増田社長の「作品」を見に行きました。
つまりは、最新作なわけです。
増田社長の全著作を読み、それらのほとんどを文字に起こした私は、表現者としての増田社長に注目しています。
今回、枚方T-SITEを見る上で、ぜひ念頭に入れておきたい言葉があります。
私はこの30年間、TSUTAYAの商材がDVDやCD(初期の段階ではそれはビデオやレコードだったが)、あるいは本や雑誌だと思ったことは一度もない。
そうした個々のモノではなく、あくまでもそれらの中に表現されているライフスタイルを、顧客に提供しているのだと私は思ってきた。
数々の映画や音楽や書籍で語られるライフスタイル。それがTSUTAYAの真の商材だ。だから、そこからレンタルという業態も発想された。
個々の商品ではなく、そこに表現されているものが商品なのだから、モノを買ってもらう必要はない。
その内容を記憶してもらうための時間に対する対価だけを頂ければいい。同時にDVD、CD、書籍を一つの店舗で同時に扱うことにもこだわった。
ライフスタイルを描き出すものがそれらの作品なのだし、であるならば、どれか一つ欠けても十分とはいえない。
とはいえTSUTAYAの創業当時は、ただこうした三位一体の店舗を創ろうとしただけで、異端視された。というのは、それらは流通経路が異なりいわば卸してくれる問屋も違う。
だからTSUTAYA以前は、レコード店と書店は全くの別物であって、交わることはなかったのだ。しかしこれこそ、顧客価値をまったく
無視した、流通側の勝手な都合による区別ではないか。
例えばハードボイルドの映画のファンなら、チャンドラーの小説だって好きだろう。そしてその主人公が好みそうなクールなジャズを聴きたいと思うかもしれない。
であるのなら、一つの店でそれらが入手できるようにしよう。
顧客価値を第一に考えれば、それが必然的に導かれる答えであるはずなのだ。私はこの業態をMPS(マルチパッケージストア)と呼び、異端視されても白眼視されても、それは絶対に譲ることのできない、一線として守ってきた。(増田宗昭『知的資本論』
結論から言うと、この言葉通りの店舗になってしました。
例えば、この「旅」のコーナーの横には旅行代理店が併設しています。ここで気になったところに行きたい!となればそのまま旅行を申し込めます。
そして、そこには様々な「提案」が施されていました。
そして、もはや蔦屋書店には欠かせない存在となった
スターバックス・コーヒーももちろんあります。
訓練されたスターバックスの店員たちが、
想定通りに来店された「プレミアエイジ」の方々へにこやかに話しかけるホスピタリティを発揮していました。
私が、今回特に大事な視点として持っていたのは
人々の肌感覚に馴染むものだろうか?ということで、
話題になり大げさになり、日常から離れれば離れるほどに
今回の蔦屋書店はコンセプトからずれていくことになる。
ゆえに、私がユーザーとしてどう感じるかな、と。
現在、オープンしたてなので店内はざわつき報道陣なども詰め寄って落ち着きがありませんが、
おそらく話題が一巡してこの場所が「日常」になった時に、
初めてそのコンセプトが達成されるのだろうと感じました。
そしてそのポテンシャルを存分に発揮されることが予想されました。
三菱東京UFJ銀行、りそな銀行が店内の内装に合わせてデザインされています。
そしてやはりここも、店内で自由に本を座席まで持って行き、読むことができるようです。
ちなみに長時間の「勉強利用」は推奨されていません。あくまで本とコーヒーを楽しむ場所のようです。
勉強利用ご希望の方は【勉強カフェ】へ。
地域性もあると思いますが、梅田にある蔦屋書店よりも、
明らかに想定された「プレミアエイジ」の方がたくさん集まっていました。
創業者の増田社長の地元は、ここ枚方です。
その目標であった「プレミアエイジ」の方が集まる場所を、最愛である地元で表現され大きく実現されそうな予感です。
本当、地元の人でたくさん賑わっています。オープン日なので私のような外部の人も結構いますが、
ほとんどはこの枚方で生活をしている人だろうなと、空気に馴染んでいる姿から確信できました。
魅力的なプレミアエイジの人々が集まれば、
そこに引かれてさらに若い層の人々が必ず集まってくるようになる。
なぜなら、そこでは自分が憧れる生活のシーンと実際に出会えるのだから。
つまり現実に、魅力的なシーンが展開されているのだから。
そこに行きさえすれば、自分もそのシーンに参加できる。
それが確かなものになれば、若い人が必ず集まる。
自分が共感できるライフスタイルを探しに訪れたプレミアエイジの人々そのものが、それに続く世代にとってはライフスタイルの指針として機能するのである。
ここにはひとつの連鎖が形成されているといっていい。そして質の高い顧客はそれだけでひとつの価値であるという命題がここでも証明されることになる。(増田宗昭『代官山TSUTAYA大人計画』)
こうやって、何気なく集まりやすいプラットホームができると
多くの人の「日常」が変わる。
「非日常」を味わうわけでなく、ごく自然と訪れる日々の活動のワンシーンの中に、
この「T-SITE」は演出される。人々の息遣いの中に、「場所」が根付く。
このようなヒューマンスケールから脱しない、人々に寄り添えるようなデザインが
この駅の近くに住む人々のライフスタイルを充実させ、本来的な
地域活性化に繋がっていくんだろうな、と、大変勉強になりました。
政治で変えられないことも、民間企業が国民の生活を変える。
これからこういうヒューマンスケールであり日常にフィットする
サービスが筆頭となり、肌感覚を変えていくものが「インフラ」として機能する世界が近づいている。
↑ライフスタイル百貨店と表現されたチラシ
さらに詳しく説明されたサイトはこちら
http://top.tsite.jp/lifestyle/lifetrend/i/28933298/?sc_cid=tcore_a99_n_adot_sm_rhiratw_28933298
ビジネスとして、視点を変えてみた場合の「枚方 T-SITE」は、
サードステージと表現されたコンセプトにマッチしています。
ファーストステージであれば、商品はモノでありさえすればよかった。つまり機能さえ満たしていれば、商品として成立した。
グラスは液体を入れておくことができさえすればよく、だからデザインまで顧慮する必要は低かった。さらにそれに続くセカンドステージでも、選ぶのは顧客自身なのだから、
デザインは付加価値などと暢気なことを言っていることもできたのかもしれない。
しかしいま私達が立つのはサードステージ、提案力の時代だ。
提案とは可視化されて初めて意味を持つ。
つまりデザインだ。提案を可視化する能力がなければ、つまりデザイナーにならなければ、顧客価値を増大させることなど、できはしない。
実際、優れたデザインとはライフスタイルの提案までがそこに内包され、表現されているものなのだ。
例えばそれが密封性の高い洒落たタンブラーなら、それを手にした人がアウトドアライフを楽しむきっかけになるかもしれないし、繊細な意匠が施されたワイングラスなら、時には良質のワインを楽しむ余裕を持とう、といったメッセージを運ぶかもしれない。(増田宗昭『知的資本論』)
だからこそ、私はこれを作品と捉えました。
ライフスタイルデザインを意識され、作り上げられた作品。
芸術は絵画や音楽だけではなく、コンセプトに波及し日常の一部となるものにステージングしていきました。
コンセプト立案も芸術の一部、アート、デザインではないかなと。
それを体現した一つとして「枚方 T-SITE」を見るのはとても興味深く、面白かったです。
人々の生活・日常に根付くことを意識され、考え尽くされた
「提案」を感じに行く場所として。
新しい時代の幕開けが、ここにあるような気がしてなりません。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
















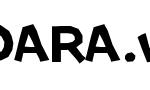









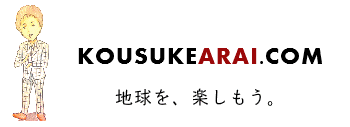
この記事へのコメントはありません。