発信はブログに全て集約させてみよう
- 2017/5/5
- THINKING
- 3 comments

FacebookやTwitter、Instagram、ブログと、4種類の発信媒体を使用して、
発信をしていましたが、
非効率極まりないな、と感じました。
であれば、全部どれか一つに集約させればいいのではないか?
こんな単純なことを思いつきました。
なので、実行します。全ての発信は、ブログのみにしてみよう。
TwitterやFacebook、それぞれ性質が異なり、発信内容を分けている人がほとんどだと思います。
現に、私もそうしておりました。
Twitterの場合は、140文字の制限があり、気軽に発信できて、バッシングも浴びづらい。
一方、Facebookは発言の重みが増し、公的なことなど(結婚報告や仲間との飲み会、仕事の打ち合わせなど)を共有するように使われている
傾向にあります。
しかし、発信しているのは同一の人物であり、Facebookの顔、Twitterの顔、など使い分ける必要はないと確信しました。
というのは、そもそもSNSというのは、本音や考えていることを共有することが目的のはずであり、
いかに自分を知ってもらうか?が本質です。
少なくとも、私にとってはそれが大きな価値です。
「いやいや、セルフブランディングというのがあって、価値のありそうな自分を演出するために使い分けるのがお利口さんなんだよ?」
という意見をお持ちのかたもいらっしゃるかと思います。
確かに、一理あります。
信用してもらうきっかけになり、新たな仕事が舞い込んだり、人に出会ったり、
承認欲求を満たしたりできるでしょう。
そこで、
本当にそうなのか?
と、深く思考を続けた結果、偽った自分のイメージを、まるでそれが本当の私であると認識してもらう価値は皆無であると結論づけました。
Facebookでは言いづらいことも、Twitterなら言いやすい。
この論理の根本には、
どうでもいいことでタイムラインをうめないようにする相手への配慮という視点もありますし、
もちろん、迷惑をかけるような誹謗中傷・不快な発言などは慎むべきですが
本音を隠して、きれいごとを言う必要は一切ないはずです。批判さえ、恐れなければ。
このブログ以外に、好きなアーティストのファンブログを作っているのですが、
ありがたいことにだんだんアクセス数が増えてきて、日本中のそのアーティストのファンからの
コメントがたくさん届くようになりました。
褒めてくれたり、会話を盛り上げてくれるコメントがほとんどなのですが、
一部には、ブログへの批判がありました。
「死ね」「恥ずかしくないのか」「馬鹿か」
など。
このようなコメントは、以前はテンションが下がるものでしたが、
今、不思議な感覚が包むようになりました。
「死ねと思われるのは嫌だけど、批判を浴びるぐらいのことを言えたのは嬉しい」
名前も知らない、あったこともない誰かに、オンライン上で「死ね」という文字を、打つ動作を起こさせた。
意味がわからないかもしれないのですが、なんかようやく認められた気がしたんですね。
死ね=認められた、って真逆やん、と言われると思いますが、
そう思ったのは確かです。
愛の反対は無関心、って言いますが、
それに近くて、結局嫌いとか好きって感情は、表裏一体だな、と。
スルーされるのが一番嫌だ、って誰かが言ってたのですが、少しだけわかりました。
堀江貴文さんとかが、Twitterとかでよく見知らぬ誰かに、同じように、あるいはもっとひどいことを言われているのに、
一つ一つコメントしたり、口論になっているのを見て、「大変そうだな」「よく耐えられるな」と思っていたのですが、
もしかしたら堀江さんも、そのやりとりは少しだけ快感なのかもしれないな、と。
であれば、もう何も隠すことなく、本当のことを言って、いろんな批判も含めて本当のことを、言って貰えばいい、と思いました。
成長スピードもその方が早いのではないか、という仮説も伴っています。
よって、ソーシャルメディアによっていうことを変える必要もなく、
常に自分の本当に思っていることを言っていきたい、考えを発信して、批判をされるならされたい。
あとは、単純に、ブログだと書いたことを時系列で自動でまとめてくれるので、便利だというのがあります。
TwitterとかFacebookだと、大昔に自分が何をつぶやいていたのか、探すのにめちゃめちゃ時間がかかりますからね。
振り返りをするのに、まとめてくれているブログが一番便利いいです。
だから、すべての発信をブログにまとめるのがいいのではないか、という冒頭の提案にたどり着きました。
ここしばらく発信から少し距離を取り、その時間を内省=インプットにあてていましたが、やはり発信は継続的に行うことが
必要で、日々の取り組みを書き記すことは、今後10年先を見据えた時に、ものすごく重要です。
今から、日々を蓄積し、記録していく。
その言語化プロセス=アウトプットは、同時に思考整理のトレーニングにもなる。
2017年、3分の1はインプットでしたが、残りはインプットももちろん行い、さらにアウトプットを加速させていこう。
2018年を迎える頃に、また新たな気づきを得るために。
SNSの効率化、の話でした。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
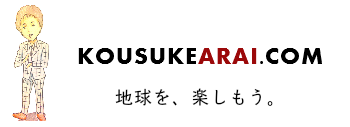
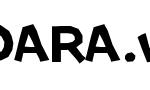










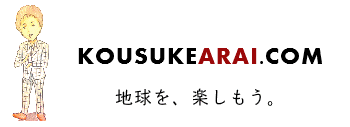
この記事へのコメントはありません。